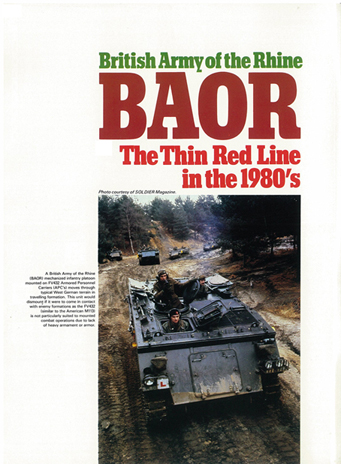 |
FV432兵員輸送車に乗車しているのは、イギリス陸軍ライン軍団(BAOR)の機械化歩兵小隊であり、移動陣形で典型的な西ドイツの地形を通行している。敵編成と遭遇した場合、FV423は(M113と同様)重火器および重装甲を欠いているので、搭乗戦闘に適しておらず、歩兵は降車しなければならない。 |
(S&T#88の記事の翻訳)
イギリス遠征軍(BEF)の後継であるBAOR(the British Army of the Rhine)は、西ヨーロッパに駐留する軍の中で、もっとも練度が高く、もっとも貧弱な装備を持つ軍隊と言われる。
歴史と伝統
近代的なイギリス陸軍は、1660年のスチュアート朝復活までさかのぼることができる。イギリスには常備陸軍が存在せず、陸軍は議会の承認によって、遠征ごとに編成されていた。平時における常備陸軍の禁止は、1689年の権利の章典によって明文化され、その伝統は今日まで残っている。
議会が大規模な陸軍を認めなかったため、17世紀の大半において、陸軍とは臨時編成の武装集団であり、その編成単位が"連隊"だった。
18世紀の連隊は、カーネル(訳注:大佐(Colonel)とは関係ない)の私有物であり投資資産である。兵士の採用や給与などの手続きが連隊内で完結しており、国は軍事費をカーネルに支払い、カーネルは兵士に食料、衣服、装備を支給した。与えられた軍事費からカーネルがどれぐらい利益を得るかは本人の良心次第だった。
封建時代、すなわち、領地を所有する者が防衛に責任を持つのが当たり前だったこの時代、士官になれるのは貴族と紳士階級であり、彼らの間で称号と任務が売買された。兵卒は放浪者から集められ、入隊すると死ぬまで兵卒だった。入隊に人物証明書は必要なく、今世紀においても中流階級の子息の入隊と「勘当」は同意義である。
初期のイギリス軍が連隊レベルで混沌としているとするなら、より上位の編成において、その混乱の度合いは増した。20世紀に入るまで、平時に連隊以上のフォーメーションは存在しなかった。さらに、軍事行動を統括する中央組織がなかった。陸軍は任務ごとに異なる司令官、軍需長官を持ち、状況に応じて、財務省、戦争局、植民局の管轄に置かれた。1905年まで、中央組織と参謀スタッフは存在しなかった。
連隊が組織として結束し、伝統が生まれたのは18世紀前半からである。"レッドコート"の軍服が標準化され、襟や袖の形に様々な意味が生まれた。連隊には王旗と軍旗が支給され、戦場での目印となると同時に、バトルオーナメントをとりつける場所となった。
18世紀、国王の主導によって連隊に番号がつけられると、連隊は独立性を持つようになった(それまで連隊は、カーネルの名前で呼ばれていた)。連隊番号は19世紀の軍制改革でも生き残った。同時に、竜騎兵(Dragoons)、擲弾兵(Grenadiers)、
火打ち石銃兵(Fusiliers)などの呼称も生まれ、それらは今日でも用いられている。
この時代、イギリスは大陸におけるいくつかの継承戦争に参加し、フランスを破り、海軍力によってアメリカとインドに一大植民地を作った。
1763年までに、イギリスはヨーロッパ諸国の嫉妬と嫌悪の対象となり、それに続くアメリカ独立戦争においては、武装市民および敵対的な中立国を相手に戦った。
独立戦争当時のイギリス陸軍は、絶対的な兵士の数が不足していた。議会がいかなる徴兵制も拒絶したため(1916年まで)、ドイツ傭兵を雇わなければならなかった。アメリカ軍と戦うために、イギリス陸軍に「軽歩兵(Light
infantory)」が生まれた。これは本隊の正面に歩兵が展開し、主力部隊の援護に当たるものだった。軽歩兵は、その後ジョン・ムーア卿によって発展し、フリントロック式ライフルで武装するライフル歩兵が生まれた。これらのエリート部隊は、今日でも「ライトインファントリー」と「ロイヤルグリーンジャケット」としてその名称が残っている。
サラトガとヨークタウンにおいて大敗を喫しアメリカ植民地を失った後も、イギリス陸軍"レッドコート"の評判は、戦火下の冷静さと、熟練した「ブラウン・ベス(制式マスケット銃)」の使用により、潰えることはなかった。
ウェリントンの勝利
 独立戦争後、イギリス・ロイヤル海軍は廃れ、陸軍は植民地の警邏組織になった。しかし、フランス革命の騒擾とナポレオンの台頭によって、陸軍は再び脚光を浴びることになる。
独立戦争後、イギリス・ロイヤル海軍は廃れ、陸軍は植民地の警邏組織になった。しかし、フランス革命の騒擾とナポレオンの台頭によって、陸軍は再び脚光を浴びることになる。
いくつかの不幸な遠征の後、有能なヨーク公によって改革されたイギリス陸軍は、イベリア半島でフランス軍を破った。ナポレオンの弱点は伸びきった補給(ロシア、イベリア半島)にあり、ウェリントン公爵は補給を重視することで優位を得た。ワーテルローの戦い(1815年)までイギリス軍を勝利に導いたのは、軽歩兵による散兵戦だった。
パクス・ブリタニカ(イギリス帝国の最盛期)に入ると、議会は陸軍の解体を働きかけ、ウェリントン公爵は補給組織を解散することで実戦部隊を温存した。兵卒の教練には暴力が用いられ、生活条件は厳しく、不衛生だった一方で、騎兵は、ヨーロッパ諸国の驃騎兵(Hussars)や槍騎兵(Lancers)のスタイルを模倣した。庶民院議員John Bright(ジョン・ブライト)は陸軍を「上流階級のための海外の余暇システム」と非難した。
次のテストはクリミア戦争だった。悲惨な軍事制度と数十年の閑却にもかかわらず、陸軍の忠誠と奉仕は不滅だった。1852年のバーケンヘッド号事件は、ビクトリア朝のイギリス陸軍の勇気と練度を象徴する事件である。南アフリカのケープタウンから出港し、直後に沈没したこの英軍輸送艦には、第74ハイランダー連隊が乗船していたが、彼らは甲板に整列して女子供を救命ボートに乗せた。638名の兵士のうち454名が溺死した。
この戦争では、テレグラフや新聞によって、戦場の様子がはじめて一般に報道された。アルマ、インケルマン、バラクラヴァで激戦が行なわれ、人々が兵士の窮状を知ると、軍事改革と兵士へのケアが求められた。その後の50年間、ゆっくりであったが兵役期間の短縮、生活環境の改善、兵卒への教育が実施された。
ビクトリア朝において、イギリス陸軍は植民地の管理人だった。1750年代以降、インド大陸は東インド会社の官僚的支配化にあった。この会社は独立した陸軍を持ち、その兵士はヨーロッパ人連隊と現地のインド人、イギリス人正規兵から編成されていた。
度重なる遠征とシーク教徒との戦争は、大英帝国の版図を守りきれる以上に広げた。1842年のアフガニスタン戦争では、悲惨な撤退を余儀なくされた。
崩壊の始まりは1857年、ベンガル軍(訳注: ベンガルはムガル帝国の行政州)が反乱を起こし、思いつきで白人殺害を行なった時である。ベンガルで孤立したイギリス人社会は、救援隊が来るまで篭城し、暴動は陸軍によって鎮圧された。イギリス軍は報復として、殺害されたイギリス人一人あたり十人のインド人を処刑した。セポイの乱の後、イギリス政府は、東インド会社を解散させ、東インド陸軍ならびにインドを直接統治するようになった。ヨーロッパ人連隊はイギリス陸軍に吸収され、インド人兵士は大砲をとりあげられ、イギリス人正規兵との混成部隊に編入された。
1900年まで、イギリス軍は、イサンドルワナ(1879年ズールー戦争)、マイワンド(1880年アフガン戦争)などの例外を除き、アジア・アフリカ諸国において、練度、戦意、武器の優位性を示した。増加する帝国の紛争に対応するため、陸軍大臣Edward Cardwell(初代カードウェル子爵)とHugh Childers(ヒュー・チルダー)は、二個歩兵大隊で一連隊とし、一個大隊を植民地、もう一個を本国での訓練と新兵募集に充てた。連隊数が減るという反対にあったものの、この軍事改革は実行され、連隊名にはイギリス国内の基地名が与えられた。戦時には、テリトリアル陸軍(Territorial Army。国防義勇軍とも)が連隊に補充された。
20世紀
軍事改革を促進したのは、20世紀初頭の第二次ボーア戦争での敗退だった。未開人との戦闘に慣れていたイギリス陸軍は、ヨーロッパ人農民たちのボルトアクションライフルの前に面目丸つぶれとなった。赤いユニフォームはカーキ色となり、小火器による散兵戦が標準的な軍事ドリルのメニューとなった。
世界大戦が1914年にはじまった時、イギリス陸軍は小規模でありながらも世界最強と考えられていた。
陸軍長官のRichard Haldane(リチャード・ハルダン)が創設したイギリス遠征軍 (BEF)は、ヨーロッパで戦うための常備師団であり、テリトリアル陸軍(Territorial
Army)の師団級支援を受ける。世界大戦が始まると、補充システムは迅速に機能した。しかしながら、ここでも、ヨーロッパ諸国の徴兵制度による数百万の兵の前では、イギリス軍は寡少な兵力だった。
愛国心が呼び覚まされ、大規模な新兵募集が開始された。新たに創設された三十個師団はキッチナー・アーミーと呼ばれたが、その後の大消耗戦の結果、1916年にはイギリス初の徴兵制を実施しなければならなかった。モンスに代表される初期の勝利は、一日で60,000人の損害が出たソンムの戦いによって打ち消された。航空機や戦車の開発に表される連合軍側の産業的優位は、塹壕戦の膠着状態を打開するものではなく、戦争を勝利に導いたのはイギリス海軍の海上封鎖だった。陸軍が地上戦で勝利を収めることができたのは、より規範的な戦場、すなわち中東のアレンビー司令官によるオスマン軍の撃退だった。
世界大戦によって財政が悪化しながらも、イギリスは依然、巨大植民地のリーダーだった。陸軍の規模は戦争前の状態に回復したが、予算削減の影響は軍全体に及んだ。アイルランドの独立後、五個連隊が解散され、いくつかの騎兵連隊が「近代的合併」という名の統廃合を余儀なくされた。1930年代のイギリス陸軍は、Liddell-Hart(リデル=ハート)やCharles Fuller(チャールズ・フラー)らの研究の影響を受けながら、質素な機械化が進められた。イギリス第一の敵ドイツは、同じ発想から徹底的に陸軍を改造した。
ナチの電撃作戦が開始された1939年、イギリス陸軍は再び、人員ならびに敵軍に匹敵する兵器・武装の不足に直面した。ダンケルクからの撤退後、イギリス本土を守ったのは陸軍ではなく王国空軍だった。北アフリカでは、迅速な反抗作戦によってイタリア軍を破った陸軍が過去の栄光を取り戻したが、ドイツ軍が参戦するとシーソーゲームに墜ちた。
その後数年間は、連合国からの膨大な武器・物資の補給と国をあげての動員によって、イギリス陸軍は世界の軍隊に返り咲いた。他国との連携のおかげで、第二次大戦ヨーロッパ戦線では戦勝国となった。極東において、イギリス、インド、オーストラリア三国は、マレー作戦で不名誉な敗北を喫し、シンガポールを放棄しなければならなかった。しかしながら1944年にBill Slim将軍(ウィリアム・スリム)がビルマ戦線で日本軍を撃退し、イギリスとインド軍兵士の名誉は回復された。
第二次大戦の終わりは、大英帝国の終わりでもあった。植民地を失ったイギリスは、兵力をアフリカとアジアに降り向け、暴動を鎮圧し共産主義と戦い、新興国の国防計画を補佐した。パレスチナからの撤兵が完了すると、イギリスの防衛政策の目は、再びヨーロッパに向けられ、イギリスはNATO条約に加盟した。
1945年以降
第二次大戦後、帝国主義からの撤退によって、イギリス陸軍も縮小した。にもかかわらず、無数の一時的な軍事介入が継続中だっため、1949年から短期平時徴兵制が実施され、それは1960年まで続いた。この期間、陸軍兵士の半分は応召兵から成り、その応召兵は社会のあらゆる層から構成された。これは志願制ではありえなかったことである。
1950年代後半から60年代にかけて、海外駐留軍の縮小と核戦略への依存により、陸軍の歳費と兵力は縮小した。十年の内に、77個の歩兵大隊は56、30個の機甲連隊は19、69個の砲兵連隊は20に縮小した。連隊システムは、歩兵訓練のためのより少数の、しかし大規模な本部を持つことが求められた。
いくつかの方法が論じられ、臨時的な手段として、トレーニングのために大隊が編成された。やがて、それらの大隊は管理組織としての"師団"にまとめられた(近衛師団、スコットランド師団、キングス師団、クィーンズ師団、プリンス・オブ・ウェールズ師団、軽歩兵師団)(訳注:ここで言う師団は管理目的の組織であり、戦闘の師団とは異なる)。さらに、戦力削減により、いくつかの歩兵および機甲部隊が失われ、その結果、たくさんの古い連隊が再統合された。この再統合は、管理目的の"師団"内で行なわれ、小さな連隊は解散されられるか、より大きな連隊に吸収された。1881年の統合によって、もっとも縁遠い連隊同士が合併することもあり、伝統ある連隊名が失われることへの心理的悪感情も生まれた。過去にも陸軍はこのような変革を乗り越えており、強い連隊の精神は維持された。
組織の上層部では、1963年に国防省が創設され、陸海空軍が内閣レベルで統括された。陸軍の、その余の最高指令機構は、従前と変わらなかった。実地においては、第二次大戦の師団編成(四個大隊から成る旅団の各二個編成(二個機甲と二個機械化)、適切な数の支援機甲とサービス)から逸脱した。1975年の防衛白書によって、編成は本文中の図のように変わり、梯団指令としての旅団を廃止するかわりに、三個列中隊を四個とすることで大隊の規模を大きくした。しかしながら、1981年には"旅団"のかわりに"タスクフォース"中間指令("task force" intermediate headquarters)が導入され、第二師団司令部(Second Divsion HQ)はイギリス本国に移送、三個旅団から成る師団二個と二個旅団から成る師団一個が編成に残された。歩兵大隊は、将来機械化歩兵輸送車を導入する際に再編成される予定だった。(訳注: 第二師団の司令部はYork。第二師団の役割は、西側にワルシャワ条約軍が侵攻した時にドーバー海峡を渡り、イギリス第一軍(I (BR) Corps)の後方を守ることだった)。
アメリカ軍が個々の人物単位で兵士を移送するのと対照的に、イギリス陸軍は部隊ごと移送した。これは19世紀の"出兵"の名残りである。歩兵大隊(およびその家族)は、通常2~4年単位で駐留地を移転し、これに二年間の北アイルランドと四年間のベリーズ駐屯が加わった。平均14年間の兵役生活の中で、イギリス8年、ドイツ4年、その他の海外で2年を過ごした。
兵士
20世紀に入ると、犯罪者から募兵されることはなくなったが、兵士の多くは、工業スラムの出身者や、アイルランド、スコットランドの失業者から採用された。今日の新兵の三分の一は、学校卒業と同時に入隊した者である。成人して入隊する人物の構成は、その時の経済情勢と多いに相関関係にあるが、75%が何らかの職業に就いていた者である。志願者は、選別センターで面接を受け、適切な職能と連隊が割り当てられる。アメリカ軍が粗悪な人材でも採用するのと異なり、小規模の組織であるイギリス陸軍の入隊者の半数は、国際知能指数で中級以上である。新兵は、連隊に配属される前に、特殊技能学校もしくは師団総務本部のトレーニング機関に配属される。それ以上のトレーニングは配属先部隊で行なわれ、個人の大隊への帰属と統合が叩き込まれる。下士官および准尉に求められる水準が高いのは、大隊レベルの部隊の質が彼らによって決まるからである。
将校は、依然、暮らし向きのよい社会層、すなわち、称号を持つ家や裕福な家族の出身者であり、サンドハースト王立陸軍士官学校の卒業生、大学の学位を持つ者、あるいは将校トレーニングプログラムを受けた者である。技術職はスペシャリスト訓練を受け、キャリアを通じて全員がスタッフスクールやその他の陸軍の高次教育機関で競争しなければならない。ひとたび将校になると、アメリカ軍にはない敬意と特権を得る。社団・連隊クラブ(regimental mess)は、他のどの国にもない大きな便宜をイギリス将校に与えている。
任務
1967年まで、陸軍は海外における任務が本国のそれを上回っていた。現在、ドイツに駐留する陸軍は全体の30%であり、10%がその他の海外、残り60%がイギリス本国か北アイルランドである。本国の陸軍を統括するのはUKLF(連合王国地上軍、United
Kingdom Land Forces)司令官である。UKLFは9つの軍管区(South-East、South-West、London、North-East、Eastern、West-Midland、Scotland、North-West、Wales)を管轄し、89,000名の常備兵と58,000名のテリトリアル陸軍(Territorial
Army)を持つ。機能上、UKLFは、Salisbury Plain訓練地、Catterick、Colchester、Bulford、Tidworth、Aldershotの守備兵も管轄する。UKLFはまた、第六野戦軍(NATOの戦略介入用に温存)、第七野戦軍(BAORの増援)、第八野戦軍(本国防衛)も統括する。
戦術野戦軍に配属されない部隊は、他のさまざまな任務を受け持つ。アルスター(北アイルランド)、ベリーズ、香港に配属される大隊のほとんどは本国編制から引き抜かれる。欧州連合軍機動部隊(Allied Command Europe Mobile Force)に配属される一個大隊および支援隊は、NATO軍と習慣的な演習を行い、ヨーロッパの南北から募兵する。第三コマンド旅団は、スカンジナビア半島への緊急部隊であり、北海油田の警備部隊でもある。ロンドン、ウィンザー、エジンバラの公務は近衛歩兵、しばしば他の部隊によっても行なわれる。
UKLFの第一の任務は、募兵とトレーニングである。可能な場合、管理用の師団が地域の正規軍と別に設けられるが、募兵システムはかつての連隊時代ほど厳格なものではない。奇妙なことに、王立砲兵連隊は事実上、特定の地域からそれぞれ募兵される。空挺部隊などの他の連隊は、性質上、イギリス全域から、あるいは陸軍内部から採用される。管理用師団は、基本的な訓練機能のために、歩兵実演大隊などの特別部隊、もしくは王立砲兵、王立機甲軍団の実戦隊の補助を受ける。
1969年のIRAの攻勢以来、陸軍は北アイルランドでの極秘作戦にかかわってきた。カソリックとプロテスタントのテロリストが公然と戦争する中、紛争前のイギリス駐留軍三個大隊は、すぐに最大13個まで増強され、それらは三個旅団に編制された(ベルファーストに第三十九、ロンドンデリーに第八、アイルランド共和国との国境に第八)。
ベルファーストとロンドンデリーのIRA支配地域に秩序を回復する作戦を行なった1972年、アルスターへの派遣軍は最大21,000名だった。過去十年間のアルスター駐留軍は13,000~15,000名であり、これは終身配備の守備兵と4ヶ月の派遣兵との混成である。現在は11,000名だが、1981年中ごろに囚人によるハンガーストライキに端を発する騒動が再開されたことから、これ以上の兵力削減はないであろう。
アルスターでの平和維持任務は、陸軍の訓練計画を狂わせ、重装備兵士、砲兵、装甲兵らは、本来の任務ができなくなった。BAORにおいても、ある時は七個大隊が北アイルランド方面に引き抜かれ、その即応能力に悪影響を及ぼした。
必然的に、アルスター特有の状況に対応するため、新たな戦術と装備が開発された。哨戒と短距離の射撃技量、対狙撃戦、対暴動、爆発物処理作戦が重視された。騒乱時の陸軍の任務は扱いにくいものであり、概して、陸軍兵士が示した規律の高さは、日ごろの訓練と高い団結力のおかげである。
大英帝国の名残りの最後の植民地は、陸軍駐屯部隊によって守られいる。現在、もっとも面倒なのは、アメリカ大陸の最後のイギリス植民地、ベリーズ(以前は英領ホンジュラスと言われた)である。隣国グアテマラ共和国の敵対的な行動が駐屯部隊の増大を招いた。
現在、ベリーズには増強した一個歩兵大隊が駐留し、これは二個戦闘グループと軽砲兵、偵察戦車、ヘリコプター、RAF分遣隊の支援ユニットから成る。部隊は六ヶ月間の短期訓練を行い、ジャングル戦に備える。
1960年、キプロスがイギリスから独立して以来、イギリス陸軍は、キプロス内の三つの主権基地領域を受け持ち、一個半の歩兵大隊が常駐している。さらに、トルコとギリシャの不安定な停戦が維持される中、イギリスは、キプロス共和国の国連軍にも半個歩兵大隊を派遣、この部隊は偵察、工兵隊による増強を受けている。
地中海の反対側には、英領ジブラルタルがあり、その領土の歴史はキプロスより古い。1713年以来、陸軍は"ザ・ロック"に駐屯兵を置き、要塞化してきた。今日、一個大隊が二年の任期で派遣され、訓練のため、定期的に本国の中隊とローティションを行なう。隣国スペインとの緊張はフランコ大統領の死とともに消え、駐屯部隊の規模はおおよそ800名である。
香港は、極東に残る最後の植民地である。グルカ野戦隊が駐留、1998年の租借期限まで、隣接する新界の警備も行なう。1975年以来、軍の規模は二個大隊編制から一個(野戦隊)に削減され、これはイギリス兵の一個大隊とグルカ兵の三個大隊から成る。最近、複数の大隊が増援として中国国境に警備のために送られ、押し寄せる難民を阻止した。香港の駐屯兵は、朝鮮の国連軍に儀仗兵を派遣し、ブルネイとフィジーにはジャングル戦の訓練のため、中隊を六ヶ月間送る。
香港に駐留する兵士のほとんどはグルカ人である。19世紀初頭から、イギリスは、この頑健なネパール山岳民族を連隊に編成し、最初は東インド会社の傭兵、次にインド軍、そして1948年のインド独立後は、グルカ旅団の名で常時編制軍とした。特別な条約規定によって採用されるグルカ兵は、頑丈で忠実な兵士というだけでなく、イギリス人兵士より維持費が安い。大部分のグルガ兵は香港に駐在し、その数は五個歩兵大隊と支援隊であるが、1983年までに、一個大隊が特別協定によりブルネイに送られる。残りの大隊はアルダーショット(イングランドのハンプシャー)近郊のUKLF配属となる。
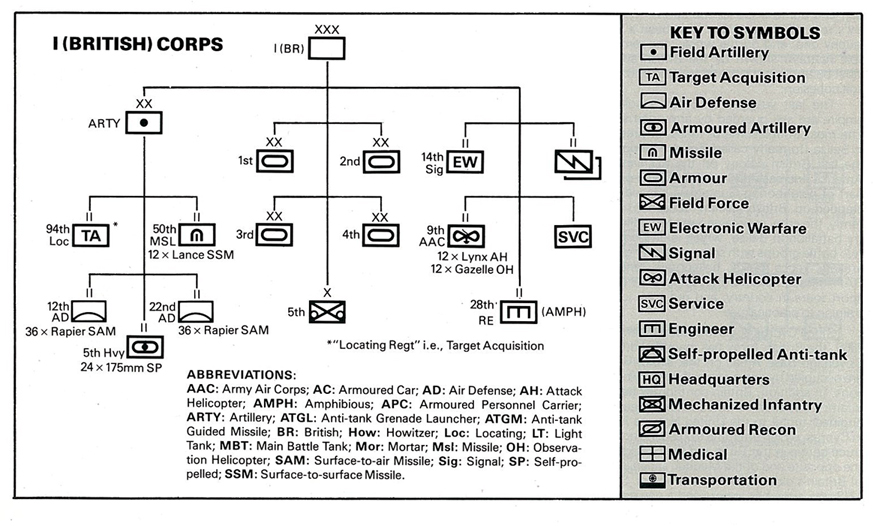
(後編に続く)